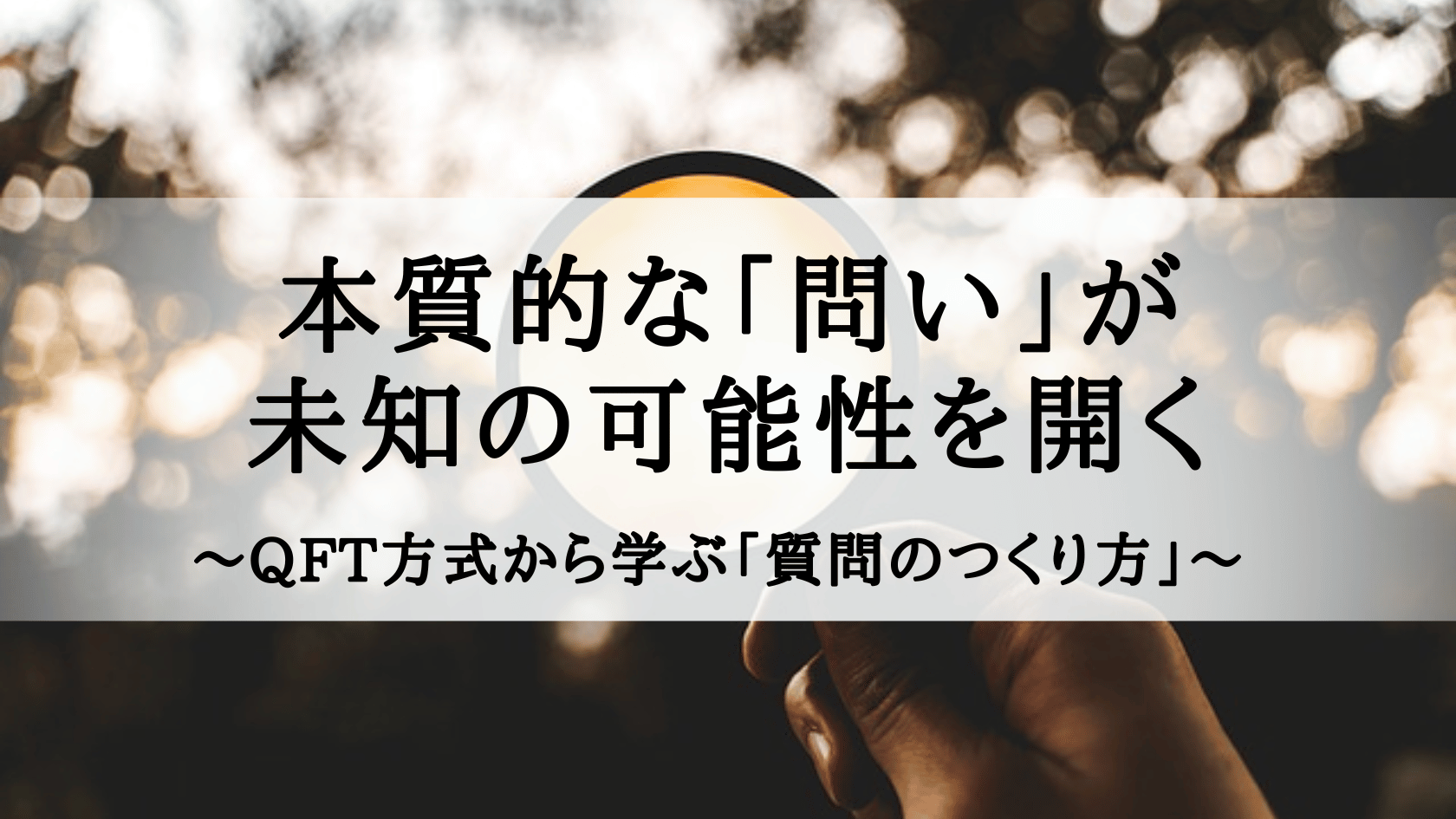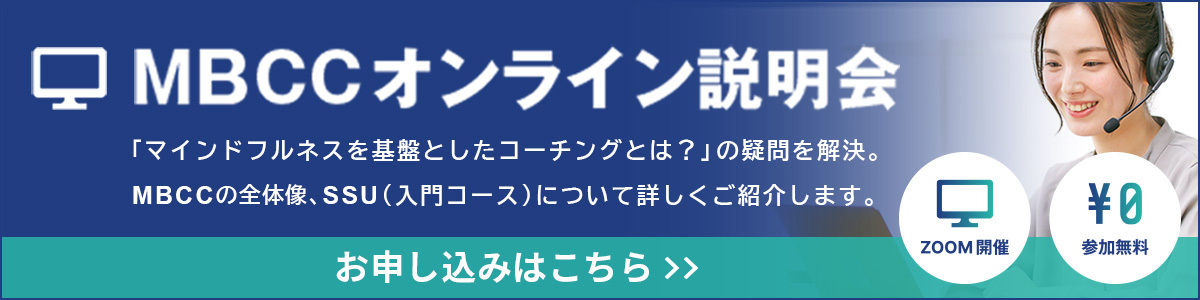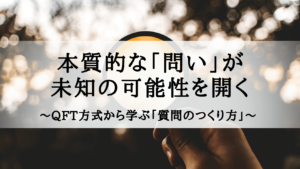
ほんとうに大切な「問い」に出会うために
コーチングにおいて質問のスキルが大切なことは、このコラムを読んでくださっている方ならよくご存知のことでしょう。また同時に、いかに質問が奥深いものであるかも。
そこで本日ご紹介するのが、QFT(Question Formulation Technique)という質問づくりの方法です。これはコーチのみならず誰もが自分自身にとって大切な問いをみつけるためのもので、セルフコーチング力の開発にもつながると思います。
コーチングを受ける人のセルフコーチング力が高まったらコーチはいらなくなる?
いいえ、そんなことはありません。
コーチングにおいて質問がパワフルに機能するのは、コーチングを受けるクライアント自身が自分にとってほんとうに大切な問いをみつけたときだからです。
コーチからの問いは、クライアントが探求すべき自分の問いを発見するための触媒になる(MBCC🄬ファウンダー、吉田典生)
またコーチが自分に問いかける大切な問いに出会うことは、コーチとして、また人としての学習プロセスを豊かなものにするでしょう。そしてクライアントと一緒に創造するコーチングの可能性を、さらに広げてくれることと思います。
なぜ「質問」がそれほど重要なのか?

宇宙物理学と科学教育の専門家、ジュリア・ブロツキー氏は、“ Why Questioning Is The Ultimate Learning Skill (なぜ「問いかけ」は究極の学習スキルなのか)”(以下、「問いかけ」は究極の学習スキル、Forbes 2020年12月掲載)の中で、成功者達が「質問」がいかに重要であるかを述べていたことを強調しています。それも、異なる分野での著名人達なのですから、さらに説得力があります。下記がそのうちのいくつかです。
“「母が私を科学者に育ててくれた」とノーベル賞受賞者である物理学者イシドール・ラビ(Isidor Rabi)は回想します。母親は「イジー 、今日はいい質問をした?」と聞いていたそうです。“
“MITのイノベーター、ロバート・ランガーは、「学生時代は、質問にどれだけうまく答えられるかで判断されるが、人生においては、どれだけ良い質問ができたかで判断される」と述べています。”
“「我々は答えではなく、質問でこの会社を運営している」と、グーグルの前CEO、エリック・シュミットはよく言っていました。”
記事の著者ブロツキー氏は、宇宙研究所のSTEM教育研究者、元NASAの宇宙飛行士インストラクター、才能ある生徒のための教育コンサルタント、そして数学教育の著者でもある才能溢れる成功者の一人でもあります。そんな彼女自身は、「問いかけ」は究極の学習スキル の中でこう述べています。
質問する能力は、学生が教育の過程で身につけることができる最も重要な生涯学習スキルの一つです。(The ability to ask questions is one of the most important lifelong learning skills a student can acquire in the course of their education.)
「質問」は何を変えるのか?

では、「質問」は何を変えているのでしょうか?
例えば、「職場の人間関係が悪いから転職をするべきか?」というテーマで悩んでいる人がいたと仮定します。この人が、異なる「質問」を持った場合の二つのケースを比較してみます。
ケース1:「転職」に焦点を充てた、いくつかの問いを持っている場合
- 「早く転職するにはどうしたらいいのか?」
- 「条件は最低でも現状維持。可能であればキャリアアップしたい。ベストな方法は?」
- 「やりがいも大事なので、チャレンジしていけるポジションを見つけるにはどうすればいいのか?」
ケース2:「転職又は他の方法や道」にも焦点を充てた、より多くの問いを持っている場合
- 「今の職場で人間関係を改善するために何ができるか? 」
- 「転職先でまた人間関係が悪かったらどうするのか?」
- 「社内異動という道はあるのか?」
- 「そもそも自分はどのくらい本気で転職したいのだろう? 」
- 「相談できる人は誰か?」
- 「自分にとって仕事とはどんな意味があるのか?」
- 「今の自分に一番重要なことはどんなことだろうか?」
上記の場合、転職を「する」か「しない」かには一つの「正解」はありません。このテーマを抱えた本人が、主体的に考えて決めていかなければなりません。
この「主体的に考えて決める」過程で、「質問」のバリエーションが多いことは、より広く深く思考をめぐらせる為の大切な材料になります。なぜなら、質問は思考をスタートする扉となるからです。沢山の扉をあけることで、探求の可能性は広がり、広がった世界には予想していなかったような「ヒント」や「答え」が隠されているのです。
ケース1とケース2を比較すると、1の方が狭い範囲での少ない質問、2の方が広い範囲(多くの視点)からより多くの質問が出ています。もちろん一概には言えませんが(ケースバイケースで様々な状況がありますので)、ケース2の方が広い世界で探求でき「より本質に迫った重要な問い」に出会う可能性は高くなると言えるのではないでしょうか。
「質問」は探求の出発点になります。バラエティに富んだ質問に取り組むことで、より重要な「質問」に出会える可能性がぐっと高まります。本コラムの冒頭で紹介したQFT(Question Formulation Technique)は、まさにこのバラエティに富んだ質問に取り組み、当事者にとって重要な質問を見つけ出す方法の一つなのです。
Right Question Institute(RQI)とは?

米国Right Question Institute (RQI) は、20年以上にわたって検証されてきた質問力養成のプログラム、QFT(Question Formulation Technique)を提供するNPOです。RQIでは、権力から遠く離れた人々も含め、全ての人々が声を上げ、意思決定に参加し、自分自身・家族・コミュニティを擁護できる活気に満ちた民主主義の構築を目標に掲げています。
RQIは、ハーバード大学教育大学院で、すべての教科・科目の教員を対象にQFTを用いたオンラインワークショップを開催しています。
MBCC®は、ビジネス分野でこのQFTを提供することを正式に認められた最初の団体でもあります。
「QFT(Question Formulation Technique)」のやり方は?

QFTの手法は、『たった一つを変えるだけ: クラスも教師も自立する「質問づくり」 』(以下「たった一つを変えるだけ 」)で詳しく知ることができます。著者はRQIの共同創設者ダン・ロススタイン氏とルース・サンタナ氏です。
下記は「たった一つを変えるだけ 」で紹介されている手法の大枠をまとめたものです。より詳しい手順については、ぜひ書籍で確認頂きたいと思いますが、下記を実行するだけでも随分と質問力が深まるのを実感できるのではないでしょうか。
ステップ1:自分たちの質問を出す
- できるだけたくさんの質問を出す。(質問する許可を与える)
- 質問を出す際に話し合ったり、評価したり、答えを言ったりしない。(安心・安全な場を提供する)
- 質問を書き出す人は、質問を出した人の発言のとおりに記録する。(すべての声を尊重する)
- 肯定文として出されたものは疑問文に転換する。(主張ではなく、質問の言い回しや問い方にこだわる)
ステップ2:出した質問を改善する
「閉じた質問」と「開いた質問」を分類する
- 「閉じた質問」:「はい」か「いいえ」ないし簡単な言葉で答えられるもの。
- 「開いた質問」:説明が必要なもので、「はい」か「いいえ」ないし簡単な言葉で答えられないもの。
※「閉じた質問」には△印をつける。残りは「開いた質問」なので〇印をつける。
それぞれの質問の価値を検討する
- 「閉じた質問」の長所と短所は何か?
- 「開いた質問」の長所と短所は何か?
質問の形態を変換してみる
- 「閉じた質問」は「開いた質問」へ
- 「開いた質問」は「閉じた質問」へ
ステップ3:質問に優先順位をつける
- 出した質問のリストから優先順位の高い質問を3つ選ぶ
- 3つの質問を選んだ理由は何かを考える?
ステップ4:選んだ質問をどのように使うのかを考える
- 選んだ質問をどうするかには多様な選択肢がある(例:リサーチする、行動を変える、関連書籍を読むなど)
ステップ5:ステップ1~4で学んだことについて振り返る
- 何が理解できたのか(あるいはできなかったのか)
- どんな気づきがあったのかなど
また、QFTのワークショップの様子を視聴できる動画(無料・英語)も二つ紹介させて頂きます。
大人を対象にしたQFT(Question Formulation Technique)ワークショップ
子どもを対象にしたQFT(Question Formulation Technique)ワークショップ
質問づくり「QFT」で養われる3つの思考力
「たった一つを変えるだけ 」では、「質問づくり」は学びを創造的に編み上げる「アート」であり、同時に「科学」であると表現しています。また、その理由はQFTのステップを踏む際に次の3つの思考力(発散思考・収束思考・メタ認知思考)が使われ、養われているからだと説明がされています。
- 発散思考 – 新しい可能性に心を開く
考えを広げていくことで、多様なアイディア、選択肢、仮説、可能性を考え出す能力のことです。そして、年齢を問わず(幼児から大人まで)練習を積むことで発散思考を養うことができます。発散思考が養われると、思考の柔軟性や学力の向上につながり、さらに難しい課題やストレスにも対処できるようになり、日常生活でも思考を応用することができるようになります。
- 収束思考 – アイディアを統合、分析、解釈する
答えや結論に向けて、情報やアイディアを分析したり、統合したりする能力です。説明したり、解釈したり、要約したり、比較したりするときに使われていて、考えをまとめるときには必ず使っている知的活動です。
<ニューズウィーク誌>の記事によれば、本当の創造力には「発散思考と収束思考を絶え間なく一体化させた状態が必要で、換言すれば、それは新しいアイディアと古くて忘れ去られたアイディアの統合を意味します。高度な創造力のある人たちは、両方の思考を使って、そうしたアイディアをまとめるのがうまいのです。学校において創造力を養うために成功しているケースでも、生徒らが発散思考と収束思考の間を行ったり来たりしていることが分かっています。」(たった一つを変えるだけ」P36より抜粋)
- メタ認知思考 – 自分が考えたことや学んだことについて振り返る
自分が学んでいることや考えているプロセスについて振り返って考える能力です。メタ認知思考があると、一つの状況で学んだことを他の状況に移して使いこなせる可能性が高くなります。しかし、調査からは、多くの大学生は基本的なメタ認知思考を持ち合わせていないことが分かっています。
自分が抱えるテーマで「QFT」を試してみる

QFTのステップを文字で読むと、時間がかかりそう、難しそう、などの印象を受け、「いつかやることのTo Doリスト」に入ってしまうかもしれません。しかし、ルール自体は一度学べば子供でもできるくらいシンプルなものです。どうか「いつか」ではなく、今、自分が抱えるテーマ(課題・悩み・学び・人生の選択など)で「QFT」を試してみて頂きたいと思います。
「たった一つを変えるだけ 」の中では質問づくりを「筋トレ」と表現していました。質問づくりの方法を知っているだけでは、筋トレの方法を知っているのと同じなのであれば、方法を知っていても変化は起きません。実践することでしか「筋肉」は養われないのです。
逆の言い方をすれば、「筋トレ」は科学的な反応で変化が起こるわけですから、QFTを練習することで3つの思考が使われ、必ず何かしらの変化や効果が出てくるとも言えます。
より多くの方が大切な「問い」に出会うことで学びや取り組みが一層進み、より大きな力を発揮していける。「自分」や「社会」を変革することにもつながるかもしれない。
「質問づくり」には、そんな大きな可能性とパワーが秘められているのだと信じています。
MBCCリサーチ担当 今村佳未
<参考文献>
- “ Why Questioning Is The Ultimate Learning Skill (なぜ「問いかけ」は究極の学習スキルなのか)”, Forbes 2020年12月掲載
- Right Question Institute(RQI) のHP(https://rightquestion.org/)
- 書籍『たった一つを変えるだけ: クラスも教師も自立する「質問づくり」 』
- 大人を対象にしたQFT(Question Formulation Technique)ワークショップ
https://mbcc-c.com/mbcc-youtube/qft_adult.html
- 子どもを対象にしたQFT(Question Formulation Technique)ワークショップ
https://mbcc-c.com/mbcc-youtube/qft_child.html